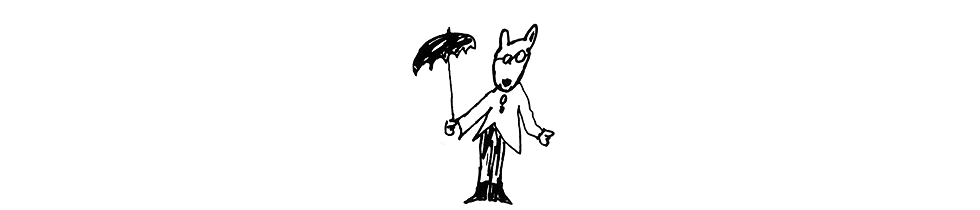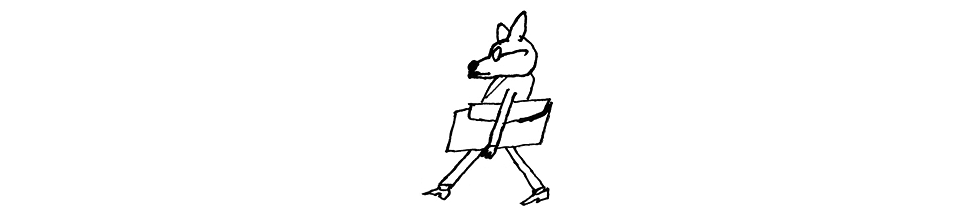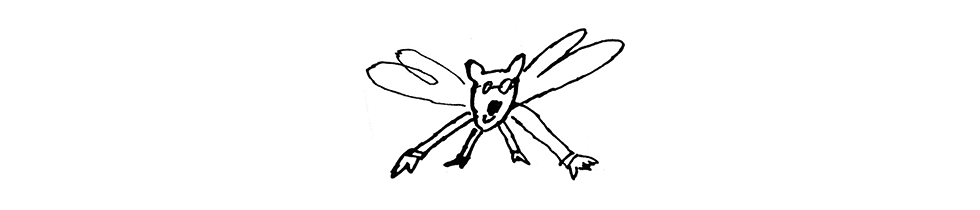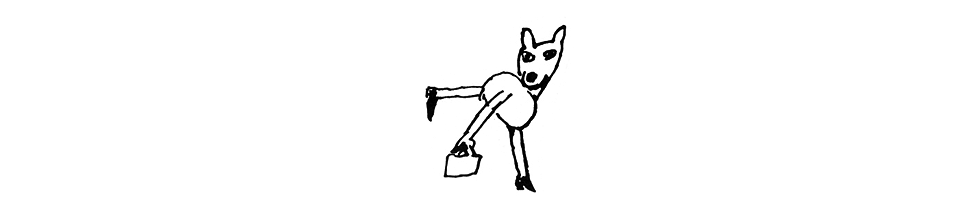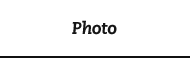原題はLESS IS MORE.
企業経営や企業の評価において、あるいは個人のキャリアにおいても「成長」は強く求められるものになっている。成長はMUSTであり、成長に異議を申し立てることは許されないような雰囲気さえある。
上場している会社の経営者は、株主たちからは常に成長を求められていて、ご苦労さまなことだと同情も申し上げる。
個人の転職を進める会社などは、成長できる職場、会社に転職すべきだ、この会社だとおあたは成長できる、なんてことも言ったりしている。
自分が年をとったからだろうか、あなたたちのいう「成長」なんて、しなくていいのじゃないの、と思うことがある。あなたたちのいう成長って、おカネをもっと稼ぐということ以外になにが含まれているのか?なんて皮肉を言いたくなることもある。
日本は人口減少が制約になって、これから経済は縮小していくだろうけど、それはそれでいいのではないかと思っている。これまでよりも少ない労働人口で、どうやって経済を維持していくのか。労働人口は減る(less)けども、創意や工夫はもっと生まれてくる(more)だろうし、これまでよりも高い賃金(more)を企業は払わないといけなくなるだろう。それは働く人たちにとってはいいことだと思う。
この本の中で著者はこんなことを訴えている。
「結局のところ、わたしたちが、「経済」と呼ぶものは、人間どうしの、そして他の生物界との、物質的な関係である。その関係をどのようなものにしたいか、と自問しなければならない。支配と搾取の関係にしたいだろうか、それとも、互恵と思いやりに満ちたものにしたいだろうか?」
政治家も、経営者も、われわれ庶民も、みんなこの問いを考えてみた方がいい。