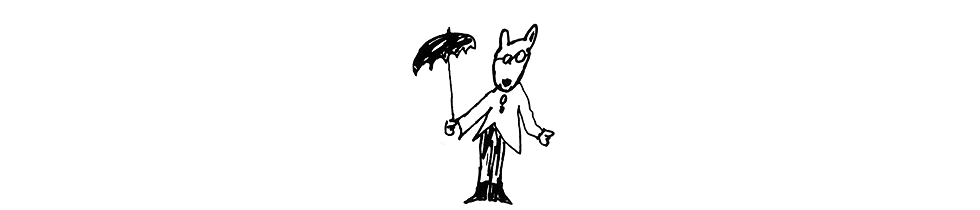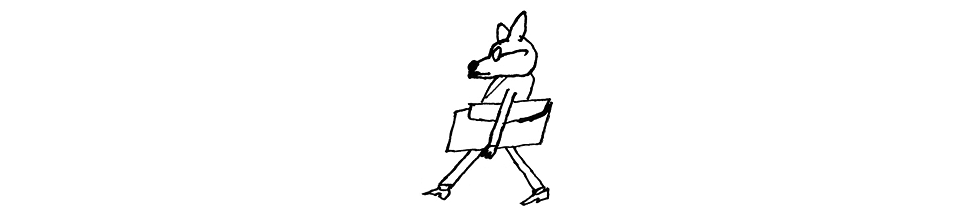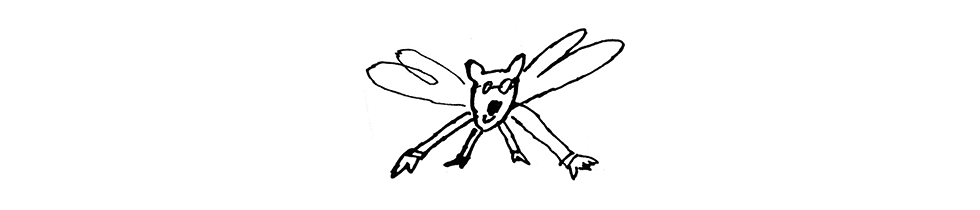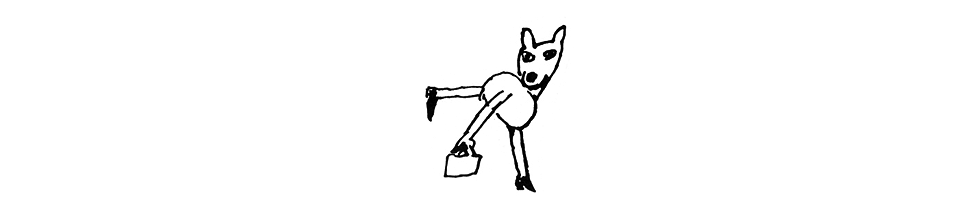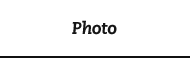「ビル・ゲイツの頭の中」
posted at 2019.10.08
新聞か雑誌か、どこでその記事を読んだのか忘れましたが、ネットフリックス(Netflix)が制作した「Inside Bill's Brain」(ビルの頭の中)という、ビル・ゲイツのドキュメンタリー番組がおもしろいという記事を読み、その番組が見たいのでNetflixに登録してみました。最初の一か月は無料でそのあと、正会員になるかどうか、決めることができます。
Netflixは以前から知っていましたし、かれらが制作した映画『Roma』(アカデミー賞受賞)は、特別に映画館で上映されていた時、作品を観てとても印象に残っています。
今回、ネットで申し込みをし、とてもスムーズな登録プロセスに感心しました。
さて肝心のビル・ゲイツに関するドキュメンタリーですが、ゲイツとの長時間にわたるインタビューに加えて、彼の幼少期、マイクロソフトの歴史を丁寧に紹介するもので、ビル・ゲイツがゲイツ財団を通して、なにを成し遂げようとしているのか、よくわかる内容でした。
ぼくはこの番組を見るためにNetflixに登録しましたが、その価値はあったなと思っています。一か月後、正会員になるかどうか、それまでにこれ以外のコンテンツものぞいてみようと思います。
先月、Malcom Gladwellの「Outliers」をオーディオブックで「読んだ」のですが、ビル・ゲイツはこの本の中でも取り上げられています。特に、彼が13歳から18歳になるまでの数年間の間に、Lakeside という私立学校で、その当時大学生や社会人たちでも好きなだけコンピューターを使うことができなかった時代、いかに彼が有利な利用環境に恵まれていたのか、それが著者がいう「一万時間」という「訓練期間」を達成する「雌伏」期間になったのか。
「ビル・ゲイツの頭の中」と「Outliers」をまとめてみると、いかにビル・ゲイツが努力の人なのか、とてもよくわかります。