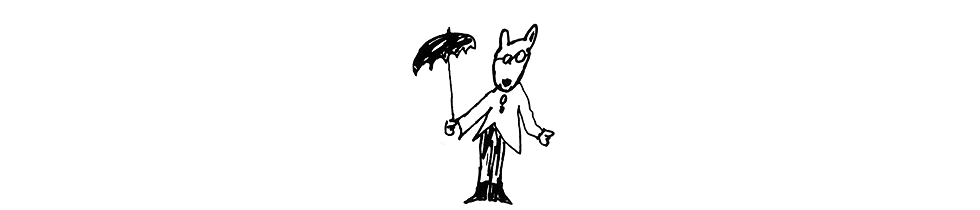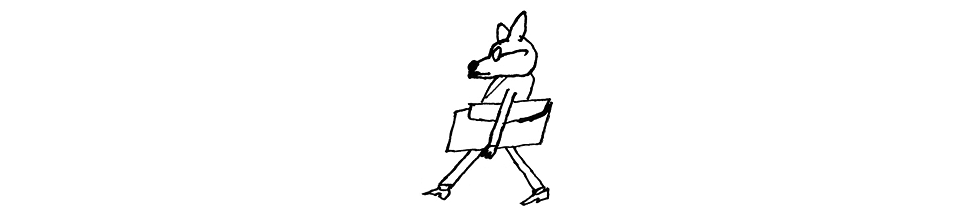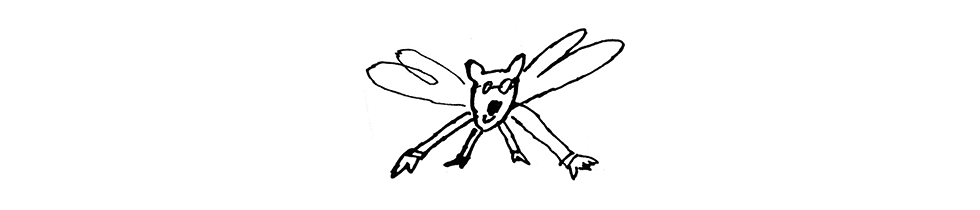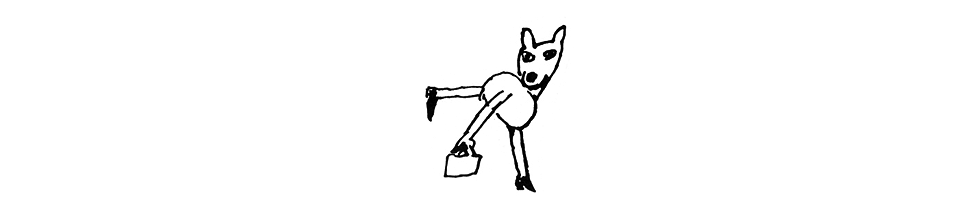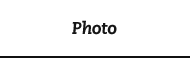著者は大学の同級生です。さらには著者である佐藤君がわざわざ僕のオフィスまで来てプレゼントしてくれた本です。なので「中立」的なご紹介ではありませんが、この本は転職だけでなく、これからのキャリアを考えているすべての社会人に参考になる情報と考え方が書かれていると、心から思いました。
この『転職のバイブル』は2006年、2008年、2010年、そしてこの2012年版とでています。これだけよく続けて出すなと感心しています。(「継続は力なり!」)
全体を通して、著者は率直です。
「転職あるべき論」には以下の5つがあげられています。
1今の会社で仕事がうまくいない人は、転職先でもうまくいかない
2転職は、年齢よりも実力
3年収が高い仕事はそれだけ高い成果を求められる
4人間関係がうまくいかないから転職するという人は、転職先でもうまくいかない
5仕事に対するプロフェッショナリズムが必須。
また、「チャンスを活かす転職成功26の鉄則」(第5章)というのがあって、このなかには、「会社に退職の意志を伝えたら、決して撤回しない」(鉄則12)とか、「引き継ぎができないなら辞めてはいけない」(鉄則13)なんていうのがあって、これらは入社前編。入社後編としては、「一事が万事!初日が肝心」(鉄則16)、「フラッシュバック症候群に負けない心」(鉄則19)、「ホームランはいらない。着実なヒットを狙え」(鉄則22)などなど、これらの鉄則も非常に参考になります。
しばらくお休みしていますが、昨年末に行ったポッドキャスティング「アイデアエクスチェンジ」にもでてもらっています。こちらもぜひお聞きいただければ幸いです。
著者と僕のベクトルは、在学中から続く時間軸のなかで、何年かごとに交わってきました。これからもお互い、健康で、しっかりと働き続けることができればいいなと心から思っています。
→アイデアエクスチェンジ