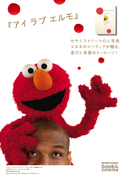カゼをひいてしまい、家でごろごろしています。カゼをひいたのは数年ぶりですが、カゼをひくことにもいいことはあります。まず第一に、食欲がなくなります。おかげで数キロ体重が落ちました。でもこれは気をつけないとまたすぐに帰ってきます。第二に、ゆっくりと本が読めます。何冊かまとめて読んでいますが、その中の一冊が、日本を代表する経済学者だった故・森嶋通夫による『なぜ日本は没落するか』。(ちなみに、カゼをひいて困ることもあります。黒犬の散歩です。カイからすると僕がカゼをひこうとそんなことは関係ありません。こっちが38.6度の熱があっても、カイには散歩が必要です。)
森嶋通夫は日本の大学に嫌気をさしてイギリスに渡ったまま、イギリスでなくなった人でした。そのように、「日本を捨てた」人は、どうも日本人の間で評判が悪いようです。でも、「日本を捨てた」からと言って、愛国心がないとは限りません。(つい最近まで、会社を辞めた人間は「裏切り者」だとするようなところが日本社会にはありました。)
個人で太りやすい体質があるように、国も偏狭なナショナリズムに陥りやすい体質があると思います。特に日本は、日本語という壁の中で暮らし、外国の意見や考え方に、直接、接することもほとんどありませんから(英語の新聞でも読んでいれば別でしょうが)、どうしても議論に多様性が乏しい上に、感情的になりがちだということもあります。だから、僕は「日本を捨てた人」の「苦言」にも耳を傾けるべきだと思っています。
この本の中での森嶋先生のお話は、端的に言って、戦後教育のもとで育った日本人が「劣化」しているということです。今の日本の大学生の大半は、大人としての成熟度、思考力などの面から見て、一昔前の高校生と同等と見なしていいのかもしれません。あるいはそれよりもひどいのかもしれません。(ひとつの「極端な例」かもしれませんが、ある席で、20名程度の大学生に、今の日経平均と、過去最高レベルのときの日経平均を聞いてみたことがあるのですが、まともに答えられる学生は一人もいませんでした。)僕が大学に入った30年ほど前にも、「かつての一橋大学の学生はこんなことはなかった」と、英語の先生に小言を言われたことを覚えています。日本の大学生の劣化はその頃からもう始まっていたのかもしれません。
悲観論連続のこの本の中で、夢のある話は、東アジア連合の構想です。中国、朝鮮半島の統一国、そして日本が連合的な組織を作るという、壮大というか、夢のような話です。21世紀から22世紀、どうやって日本は存在していくことができるかと考えたとき、近隣諸国との関係を抜本的に改善していき、EU的な関係を築いていくことではないかというアイディアです。USA=United States of Asia!
日本の村社会、封建社会の論理と、西洋社会により強くある普遍主義のせめぎあいが、明治維新以来の日本では、ずっと続いているのだと思います。その中で、森嶋先生のような方は日本社会でははじかれてきたのでしょう。でも、いつまでも村社会の論理を守っていけるほど、日本は独立国家ではないはずです。食料にしても、防衛にしても、教育さえも(この本の中で、森嶋先生も書かれていますが、東大の先生たちも、大学院教育にはアメリカに行けと生徒に指導していたという話があります)、海外、特にアメリカにおんぶにだっこです。
森嶋先生のこの本は、最初に英語で書かれたのではないかと思います。英語でのタイトルは、Japan at a Deadlock. 「行き詰まった日本」。この本が出たのは、99年のことです。残念なことに、10年ほど経った今、日本の行き詰まり状況は一層悪化しているように思えます。そういう意味で、この本の中で指摘されていることは依然として日本に当てはまります。
London Times の森嶋先生への追悼記事もあります。