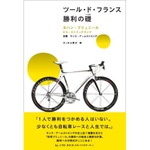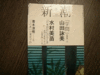『代表的日本人』(内村鑑三著)から
posted at 2008.09.11
高知県生まれだというと、坂本龍馬の名前が必ず出てきます。ですが、実は、あまり坂本龍馬のことを知りません。お恥ずかしながら、多くの人が読んだという、司馬遼太郎の『龍馬がゆく』さえも、読み通したことはありません。
どちらかというと、西郷隆盛が好きです。「天を相手にせよ。人を相手にするな。すべてを天のためになせ。人をとがめず、ただ自分の誠の不足をかえりみよ」とした、「大西郷」が好きです。内村鑑三は、明治維新がなるためには、「すべてを始動させる原動力であり、運動を作り出し、『天』の全能の法にもとづき運動の方向を定める精神」を持っていた西郷こそが、必要な人物であったとしています。まさに、今の日本には、原動力となり、運動を作り出す力と魅力を持った、西郷のような人物の登場が望まれます。
もうひとつ、西郷の好きなところがあります。西郷は、犬が趣味で、「届け物はすべて受け取らず断っていたが、犬に関するものだけは、熱く感謝して受け取った」そうです。日夜、犬と一緒に、山の中を歩き回ることを好んだというのも、素晴らしいです。
西郷隆盛について知るだけでも、内村鑑三の『代表的日本人』は読む価値があります。