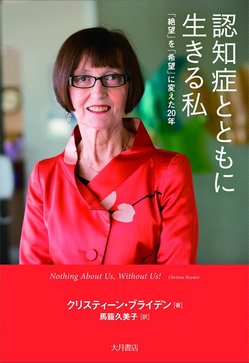『不確かな医学』(TED Books)
posted at 2018.04.30
10年前、あるいは20年前、先輩方が健康のお話をされていると、どうも話に関心を持てなかったのですが、大切な存在が命の終わりをむかえ、自分自身も身体のどこかが調子悪いことが続くようになり、医学や健康に関してとても関心を持つようになりました。
『不確かな医学』の著者は、インド人、シッダールタ・ムカジー。がんの研究者であり、2011年のピューリッツアー賞を受賞した『病の皇帝「がん」に挑む』の著者。
実はいまこの『病の皇帝』の上巻を読んでいるところですが、中休みを兼ねて、同じ著者の手軽な本を読みました。TEDのスピーチをもとにしてできた本かと思います。この本の中で、彼は医療現場の法則として以下の3つを挙げています。
1 鋭い直感は信頼性の低い検査にまさる
2 正常値からは規則がわかり、異常値からは法則がわかる
3 どんなに完全な医療検査にも人間のバイアスはついてまわる
これらは医療現場だけでなく、ビジネスにおいてもあてはまることではないかと思いながら読みました。
この本の中で、ベイズ(統計学の「ベイズの定理」のベイズ)の話もでてきます。宗教家でもあったベイズに関心を持ちました。
→TEDトーク(英語)