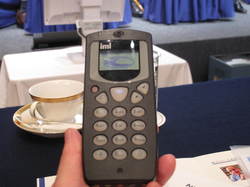以前、雇用訓練の授業を受託することを躊躇するパソコンスクールがあることを書きました。(→黒犬通信7月29日)その時紹介した理由は、受講者の就職の世話をしないといけないことが負担になっているということでしたが、今週は別の理由で、受けたくないという話を聞きました。
それは、このビジネスを受託する際の入札の存在です。値段だけで委託の可否が決められ、自分たちのサービスの質が評価されないという理由で雇用訓練のビジネスを受けたくない、というものです。
公共事業において、一納税者としては、もちろんできるだけ費用をおさえて欲しいと思うのですが、こうやって受託する企業側の当事者から直接お話を伺うと、そちらのお気持ちもよくわかります。
医療においても、まったく同じような話を聞きます。自分の技術が評価されない、一律の対価しか払ってもらえない、違いを理解してもらえない、と。
一円でも安い方がいいというのもわかります。特に公共事業の場合には、特定の企業との関わりに不透明さがないように、数字で表すことができる値段が決め手になってしまうこともあり得ると思います。
でも、一般論としてですが、世の中には、値段だけで決めてもらいたくない商品やサービス、あるいは値段以外の理由で買い物をするというケースがあっていいように思います。教育や医療、介護などはその一例でしょう。
日頃の買い物に関して言うと、商店街での「ごひいき」というような言葉がだんだん僕らの記憶から薄れていき、いろいろと失ったものが多いように思います。どちらかというと最近の僕は、ネットよりも、現実に手に触れることができる空間や街並みを大切にしたいと思っている人間です。マクロ的に観たとき、ネットとリアルのビジネスのバランスがもっと考えられてもいいように思います。それは、これまで何百年、何千年の間に作り上げられた、人間にとってもっとも最適な空間と時間という観点からです。ネットビジネスの人間には、理想のバランス像を持っている人、そのようなことを真剣に考えてきた人は、ほとんどいないように見えます。
最初の話にかえると、パソコンスクール全般は、現在厳しい状況にあるので、雇用訓練のビジネスは欲しいというところは多いのですが、それに頼り切ることなく、自分たちでビジネスを切り開こうとしているスクールも一部にはあります。そんなところには、頑張っていただきたいと心から応援しています。