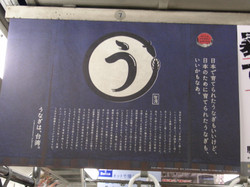今日はある方にお会いさせていただくために午後都内へ。大学生のころからファンだったかたなので、お会いできてうれしかった。
その後、柏まで行ってレイソルとヴァンフォーレのJ2一位、二位対決を見た。アウェー側には、写真のとおり、山梨から大勢のファンが来ていて力の入れようがしっかりと伝わってくる。甲府は甲斐犬たちのふるさとということもあり、甲斐犬愛護会の展覧会にもなんどか参加している我が家としてはひいきにしているチームというか、フランチャイズのひとつ。

試合はレイソル楽勝ムードだったのに、一人退場者がでてからは完全にヴァンフォーレに試合は傾き、終わってみると2−2。最後の10分程度でやられてしまった。終了後はヴァンフォーレ勝利のムードが漂っていた。
ナイターの試合としては最高の天気で空には写真のような月が。

ところで、Jリーグは、一体、なんのためにやっているのだろうか?
というのは、最近発表された昨年度の各チームの収支報告を見ながら、これだけ赤字でいいのだろうか?!という素朴な質問があるからだ。これだけの規模で行われている活動であればおカネの帳尻があわないものは長続きできない。厳しい言い方をすると、黒字でないものは社会から求められていないのかもしれない。
一見黒字になっているチームも、広告収入の比率が異常に高いところは、株主となっている企業や自治体からの実質的な補助金で支えられているということだろう。そんなところは、親の考えが変われば(日本テレビ)、子どものサッカーチームはたいへんなことになる(ヴェルディ)。
カネの亡者なんて大嫌いだけど、カネの帳尻があっていない人間の活動は、継続できない。カネのことを忘れていられるのは子どもの特権で、大人になるとそういうわけにはいかないよ。
J1チームの中で感心するのは山形。ここは入場料収入(3億39百万円)が、広告収入(1億94百万円)を上回る。僕の会社がユニフォームスポンサーになっている福岡よりも、入場料は多い(福岡は入場料収入2億1百万円、広告収入4億24百万円)。人口でいうと圧倒的に大きな福岡のチームが、絶対金額でも、山形のチームよりも少ないとは、残念な話だ。福岡のみなさん、もっとレベスタに行って下さい。(そして当社の資格試験も受けて下さい!)
入場料収入>広告収入となっているチームは、山形以外では、仙台、東京Vしかない。
プロ野球チームの経営はどうなっているのだろうか?野球の場合には、チーム名の一部に、株主企業の名前をつけることができ、それが大きな広告効果を生んでいるのだろうし、株主側には大きな満足感もあるのかもしれないが、Jリーグの場合、背中や胸にスポンサー名が入ったりする程度。アビスパの場合も、福岡市がかなりの資金援助をしてきたとお聞きしている(それは公表されていることだけど)。
Jリーグの理念は立派だと思うけど、あまり「清貧の思想」にとらわれていると、継続できないし、考える事、やる事のスケールも小さくなってしまう。
もう一度、最初の質問にかえるのだけど、Jリーグは一体なんのためにやっているのだろうか?
土曜日の夜、満月の夜空のもと、「そこそこのレベル」の試合を楽しみ、なんとなくハッピーな気持ちなって家路に着く人達は、もしJリーグの試合がもう見られなくなったとしたら、どうするだろうか。スペインやイタリアでは、サッカーは人生の一部になっているといわれるけど、日本ではどうなんだろうか?日本にはバレーもあれば、バスケットもあり、柔道、相撲、野球などなど、遊びというか、楽しませてくれるものが、実に多い。だからサッカーがなくなると、ちょっと寂しくはあるけど、他のもので代替できるだろうか?
試合後、グループで来ているサポーターたちの楽しそうな話に耳を傾けながら、日立のグラウンドから駅近くの駐車場まで歩いている間、そんなことを考えていた。