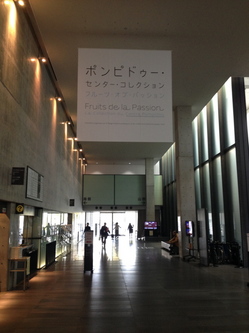学びと観光のスペイン旅行だった②
posted at 2025.03.05
スペインから返ってもう一週間以上になる。ようやく2回目を書く。
バルセロナの集まりのあと、マドリッドに移動。土曜日、日曜日と二日間観光に充てられたのはとてもラッキーだった。
土曜日はプラド美術館で丸一日過ごした。スペイン絵画の総本山!ベラスケス、エル・グレコ、ゴヤ。事前にFinancial Timesで「プラドではこの10作品を見るべし」という2023年にあった記事を読んでいたから、そこで取り上げられていた作品は見逃さないようにしたのだけど、一作品だけ、Boys on the Beach (1910)が貸し出しになっていて見られなかったのが心残り。またプラドにいく理由にしよう。
日曜日はチケット販売サイトで電子チケットを購入してレアル・マドリッドの試合を観戦。モドリッチがすばらしいシュートを決め、試合をコントロールするし、39歳のスタープレーヤーの活躍を見れてラッキーだった。レアルの試合観戦もまたマドリッドに行く理由になるなあ!