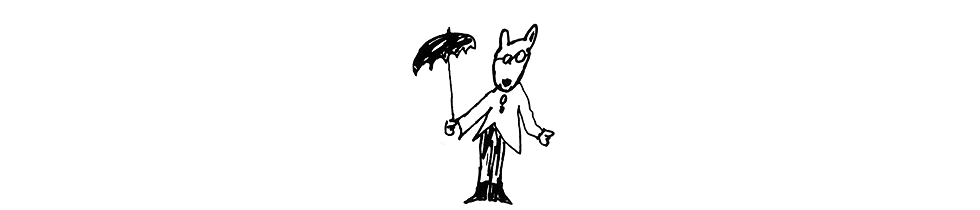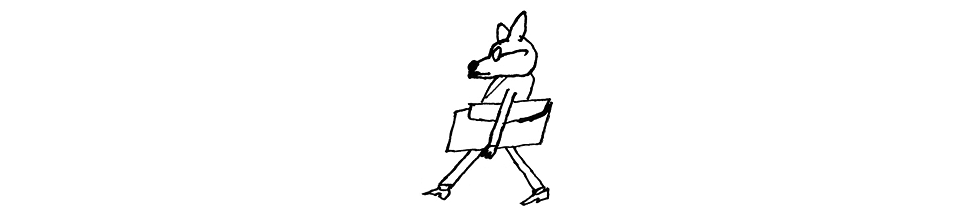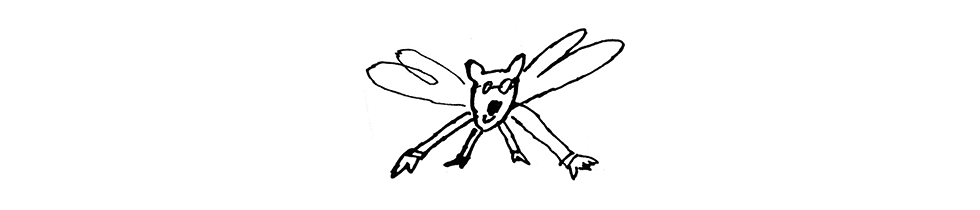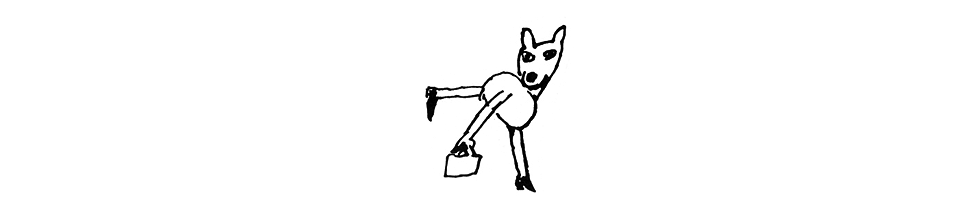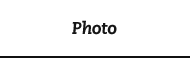『神話の力』(ジョーゼフ・キャンベル、ビル・モイヤーズ著)
posted at 2010.07.23
神話学者のジョーゼフ・キャンベルに、ジャーナリストでキャンベルの熱烈な読者でもあるビル・モイヤーズが行ったインタビューを一冊の本にしたもの。現在まだ読書の途中ですが、非常にすばらしい本です。資本主義が大きな曲がり角を迎え、自然・環境との共生、生物多様性を根本から考えないといけない地点に人類がたつなか、考えるヒントが詰まった一冊と思います。
「科学が信仰を大掃除」(ソール・ベロー)してしまっても、人類は新しい神話を必要としていること、その新しい神話は、地球という惑星とその上のあらゆる人間について語ったものであるだろうこと。しかし、その神話は、これまでのすべての神話とまったく同じように、「個人の成長ー依存から脱して、成人になり、成熟の域を通って出口に達する。そしてこの社会との関わり方、またこの社会の自然界や宇宙との関わり方」を、新しい神話も語らなくてはならないこと。ただ、一つ違いがあるとすると、新しい神話が語る社会は、この惑星全体の社会でなくてはならないこと。
第一章の終わりに、これまで僕が読んだ中でもっとも美しい手紙のひとつと言える手紙が紹介されています。それは、1852年頃、先住民部族であるインディアン部族の首長であるチーフ・シアトルに、合衆国政府が土地購入の話を持ちかけた時の返答です。
「ワシントンの大統領は土地を買いたいという言葉を送ってきた。しかし、あなたはどうして空を売ったり買ったりできるだろう。あるいは土地を。その考えはわれわれにとって奇妙なものだ。もしわれわれが大気の新鮮さを持たないからといって、あるいは水のきらめきを持たないからといって、それを金で買えるものだろうか?この大地のどの一部分も私の部族にとっては神聖なものだ。きらきら光る松葉のどの一本も、どの砂浜も、暗い森のどの霧も、どの牧草地も、羽音をうならせているどの虫も。あらゆるものが私の部族の思い出と経験のなかでは尊いものだ。われわれは血管に血が流れているのを知っているように、木々のなかに樹液が流れているのを知っている。われわれは大地の一部であり、大地はわれわれの一部だ。香り高い花々はわれわれの姉妹だ。クマ、シカ、偉大なワシ、彼らはわれわれの兄弟だ。岩山の頂き、草原の露、ポニーの体温、そして人間、みな同じ家族なのだ。」
「われわれが自分の土地を売るとしても、大気はわれわれにとって貴重なものであることを、大気はそれが支えるあらゆる生命とその霊を共有していることを、忘れないでほしい。」
「あなたがたは、われわれが自分の子供たちに教えたのと同じことを、あなたがたの子供たちに教えるだろうか。大地がわれわれの母だということを?大地に降りかかることは大地の息子たちみんなに降りかかることを。」
「われわれはこのことを知っている。大地は人間のものではなく、人間が大地のものだということを。あらゆる物事は、われわれすべてを結びつけている血と同じように、つながりあっている。人間は生命を自分で織ったわけではない。人間はそのなかでただ一本のより糸であるにすぎない。」
「最後のひとりになったレッドマン(インディアンのこと)が未開の原野といっしょにこの世から消え去り、彼の思い出といえば、大平原を渡る雲の影だけになってしまったとき、これらの海岸や森林はまだここにあるだろうか。私の部族の霊が少しでもここに残っているだろうか。」
「われわれが土地の一部であるように、あなたがたも土地の一部なのだ。大地はわれわれにとって貴重なものだ。それはまたあなたがたのためにも大事なものだ。われわれはひとつのことを知っている。神はひとりしかいない。どんな人間も、レッドマンであろうとホワイトマンであろうと、おたがたいに切り離すことはできない。なんといっても、われわれはみな確かに兄弟なのだ」
冒頭から最後の一節まで、一部略しながらご紹介してしまいました。この手紙を読んでいて、チーフ・シアトルの偉大な思想に心を揺さぶられました。そして資本主義や物質主義が行き詰まった時、彼の思想が何世紀かのときをへて蘇る日がきっと来るだろうという予感がします。