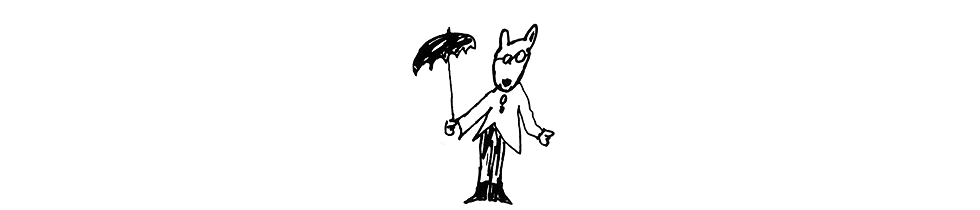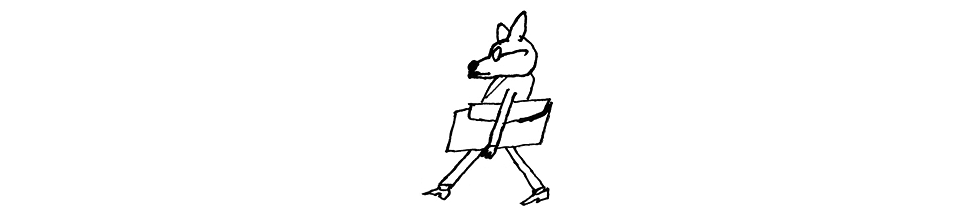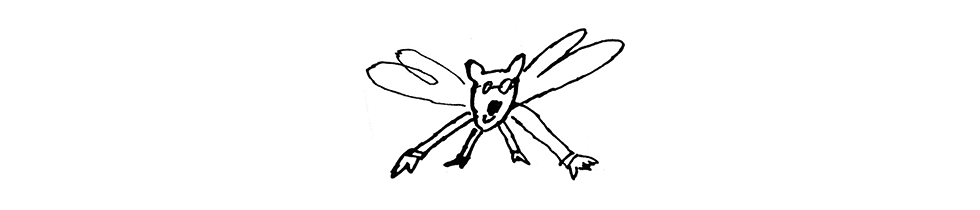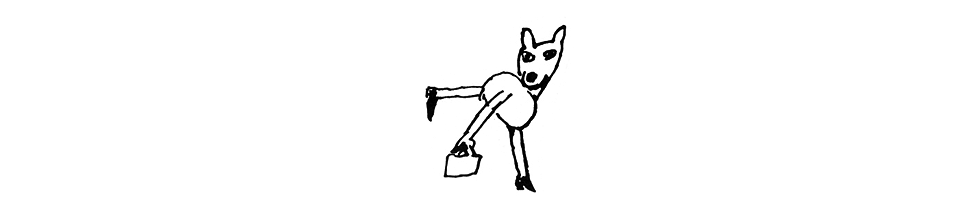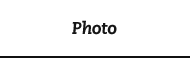『貧困の僻地』(曽野綾子著)
posted at 2010.10.31
雑誌「新潮45」に連載されていたエッセイをまとめたもの。2006年12月から2008年8月まで連載されていた。曽野さんのエッセイは結構読んでいる。産經新聞に書かれている「透明な歳月の光」も毎回読んでいる。小説はそれほど読んでいるわけではないので、いい読者とは決して言えないと思うけど。
曽野さんの行動で心から立派だなと常々思っていることがある。それは彼女が始められた海外邦人宣教者活動援助後援会(JOMAS) が資金援助された現場を、ご自身の足で訪問されご自身の目で確認されていることだ。エッセイにでてくる援助の現場というのは、半端なところではない。アフリカの貧しい国、その国の首都からクルマで何十時間もかかるような、途中で事故にあったら生きて帰ることができるのかとヒヤヒヤするようなところ。そんなところに、日本人シスターたちが献身的に働いているということはもっとすごいことなんだけど、お金を出すだけでなく、実際の現場を見に行くという曽野さんの行動力にも同じように感心する。(援助の現場をよくご覧になられているからか、こんなことも書かれている。「私は最近、国連と名のつくところへの寄付は一切しないことにしている。使い道が正確にわからないのと、膨大な数の国連職員が、世界各地で特権階級の暮らしをしているのを見ているからだ。あれは世界的な失業救済事業ではあろう。」)
曽野さんがなんども繰り返し書かれていることのひとつ。日本に住むわれわれの生活は、世界の貧しい国と比べると物質的、制度的には天国のような状態にあるのだけど、自己憐憫のかたまりになっている人が多いものだから、悪い結果はすべて他人や社会のせいにして自分の責任を受け入れようとしない人があまりにも多くなっている。それは一昨日お会いした服部文祥さんとの対談の中でも出た話だった。
週末によく行く本屋には、曽野さんの『老いの才覚』という新書が、複数のコーナーに置かれていた。どれだけの読者がいるのかは知らないけども、老いることを受け入れていく覚悟のようなものを彼女の本から得ようとしている人たちがいるのかと思う。
塩野七生さんもそうだけど、曽野さんもご自分の目で見たことを、ご自分の頭で考えられている。そしてご覧になられている世界の幅はかなり広く、深い。そこが二人に共通する魅力かなと思う。