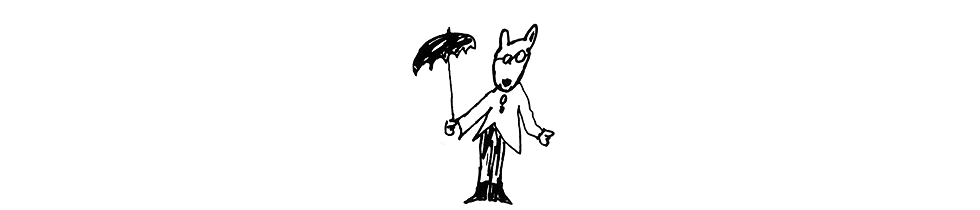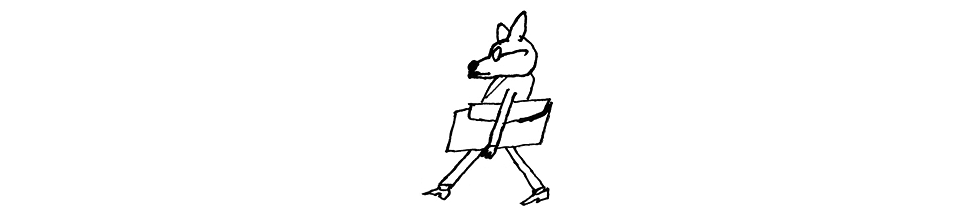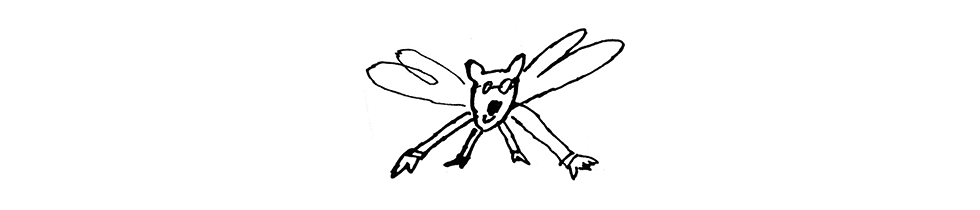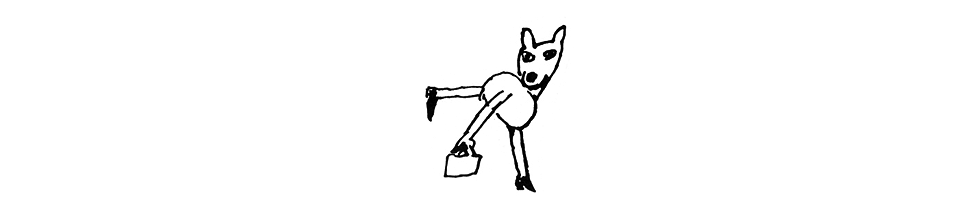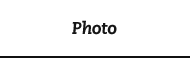『祖国より一人の友を』(海老坂武著)
posted at 2008.09.20
(以前、一度ご紹介したことがある)僕が大学1年のときのフランス語の先生の自伝三部作の完結編。1972年から1989年までの先生の思考と行動が描かれています。僕が大学に入ったのは、1979年。その年の4月から1年間、海老坂さんのフランス語の授業を受けました。この本の中には、海老坂ゼミに入っていた、僕の同級生3人の名前がでていて(単に引っ越しを手伝ってもらった、ということですが)、とても懐かしくなりました(そのうちの一人である香月君とは、まだ年賀状の交換をしていますが、ほかのふたり、後藤君と坂下君は、いま、なにをやっているのか?)。
この本の中には、一橋大学で教えていたときの話はほとんど出てきません。仕事として、割り切っていらっしゃったのではないかと思います。(その頃、一橋大学にはもうひとり、鈴木道彦先生というフランス語の先生がいて、鈴木先生は、プルーストの『失われた時を求めて』の個人訳という大きな仕事を完成されます。鈴木先生のことも、この本の中には、出てきます。)
朝吹登水子の紹介でサルトルに会った時のこと、ポール・ニザンの未亡人を訪問したことなど、ページをめくりながら、ちょっとドキドキしてしまった。タイトルは、『アンティゴネー』の中の一句からとったものだそうです。12歳で敗戦を迎えた、それまで「愛国少年」だった一人の人間にとって、「愛国」は、実にくだらなく、むなさしいものにしかすぎなかった。
ほんの一学年、1979年P組(フランス語)の一人の学生のことなど、先生の方では覚えているはずもないのですが、僕の方は、何となく、海老坂さんの本を何冊も読んでいて、特に、この『祖国より一人の友を』を読んで、一人の人間としての海老坂武に、とても親近感と懐かしさを持ってしまいました。